過去見積件数20,000件以上!大阪府全域対応!
その他地域(兵庫県・奈良県・滋賀県・京都府など)
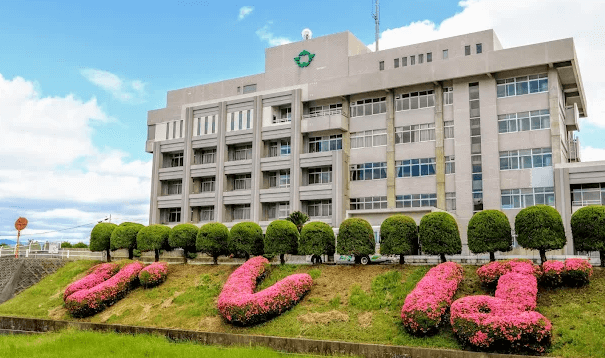
「香芝市にある古い実家を解体したいけど、費用が高くて…」
「空き家の管理が大変だから解体したいけど、使える補助金はないかな?」
香芝市に所有する空き家や老朽化した建物の解体をお考えで、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。解体工事にはまとまった費用がかかるため、少しでも負担を減らせる補助金制度はぜひ活用したいですよね。
この記事では、香芝市で利用できる解体工事の補助金に関する最新情報を、専門家の視点から分かりやすく解説します。
残念ながら、現在香芝市単独の解体補助金は受付を終了していますが、代わりに利用できる奈良県や国の制度があります。さらに、解体後のリフォームや新築に使える補助金もあわせてご紹介します。
この記事を読めば、あなたが利用できる補助金の種類や申請方法、注意点まで全て分かり、安心して解体計画を進める第一歩を踏み出せます。
香芝市の解体補助金の現状【2024年最新】
まずは、香芝市の解体補助金の現状について、最新情報をお伝えします。
結論 香芝市単独の解体補助金は現在受付終了
結論から言うと、2024年6月現在、香芝市が独自に行っている解体工事に関する補助金制度は受付を終了しています。
香芝市では以前、「香芝市老朽危険空き家等除却促進事業補助金」という制度がありましたが、市の公式サイトによると令和5年度の申請をもって受付が終了しています。
そのため、現時点では香芝市から直接、解体費用の補助を受けることはできません。
(参考:香芝市「香芝市老朽危険空き家等除却促進事業補助金について」)
代わりに利用を検討できる奈良県の補助金制度
「香芝市の補助金がないなら、諦めるしかないの?」とがっかりされたかもしれませんが、ご安心ください。
香芝市にお住まいの方でも、奈良県が実施している補助金制度を利用できる可能性があります。
特に「奈良県住まいの安全・安心・快適・省エネ・長寿命化促進事業」は、耐震改修やリフォームとあわせて、空き家の除却(解体)も対象となる場合があります。
この制度の詳細は後ほど詳しく解説しますが、市の制度がないからといって諦めず、県の制度を積極的に検討しましょう。
香芝市空き家等対策計画と今後の見通し
香芝市では、増え続ける空き家問題に対応するため「香芝市空き家等対策計画」を策定し、対策を進めています。
この計画に基づき、将来的には新たな補助金制度が創設される可能性もゼロではありません。 空き家の解体を検討している方は、定期的に香芝市の公式サイトで最新情報をチェックすることをおすすめします。
(参考:香芝市「香芝市空き家等対策計画」)
【一覧】奈良県・香芝市のリフォーム補助金
解体だけでなく、その後のリフォームや新築をお考えの方も多いでしょう。ここでは、香芝市で利用できるリフォーム関連の補助金制度を一覧でご紹介します。解体と直接関係なくても、住宅に関する費用負担を軽減できる貴重な制度です。
奈良県住まいの安全・安心・快適・省エネ・長寿命化促進事業
奈良県が実施している総合的な住宅補助金制度です。耐震化やバリアフリー、省エネリフォームなど幅広い工事が対象となります。
- 補助対象工事
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 長寿命化のためのリフォーム
- 空き家の活用・除却(※市町村の補助との協調が条件の場合あり)
- 補助金額
- 工事内容により異なり、最大で100万円以上の補助が受けられる場合もあります。例えば、耐震改修工事では最大50万円、省エネ改修では最大30万円など、複数のメニューが用意されています。
- 主な条件
- 奈良県内の自らが居住する住宅であること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(耐震改修の場合)など、工事内容によって条件が異なります。
(参考:奈良県「奈良県住まいの安全・安心・快適・省エネ・長寿命化促進事業」)
香芝市三世代同居・近居促進事業
香芝市が独自に行っている、子育て世代を応援するための補助金です。親・子・孫の三世代が新たに同居または近居するために住宅をリフォームする場合に利用できます。
- 補助対象者
- 三世代で同居・近居を始める方
- 申請時点で、中学生以下の子どもを扶養し同居している世帯
- 補助金額
- リフォーム費用の2分の1、上限30万円
- 主な条件
- 新たに同居または近居(香芝市内で直線距離2km以内)を開始すること。
- 市税の滞納がないこと。
(参考:香芝市「香芝市三世代同居・近居促進事業」)
国の補助金 子育てエコホーム支援事業
国が実施している大規模な補助金事業で、省エネ性能の高い新築住宅の取得や、省エネリフォームを行う子育て世帯・若者夫婦世帯を支援するものです。
- 補助対象者
- 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)
- 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
- 補助金額(リフォームの場合)
- 工事内容に応じて設定された補助額の合計。上限は20万円~60万円(世帯属性や既存住宅の状況による)。
- 対象工事の例
- 開口部の断熱改修(内窓設置、外窓交換など)
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、節水型トイレなど)
(参考:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」)
空き家解体で補助金を利用する際のポイント
補助金を利用して空き家を解体する際には、知っておくべき重要なポイントが3つあります。後で「知らなかった」と後悔しないように、しっかり確認しておきましょう。
補助対象となる空き家の主な条件
補助金の対象となる空き家には、一般的に以下のような条件が定められています。
- 長期間使用されていないこと
おおむね1年以上、居住や事業などの目的で使用されていないことが条件となる場合が多いです。 - 老朽化・危険性が認められること
自治体によっては、職員による現地調査で「不良住宅」や「危険な空き家」と判定される必要があります。 - 個人が所有していること
法人が所有する物件や、販売・賃貸を目的とした物件は対象外となることがほとんどです。 - 公共事業の補償対象でないこと
道路拡張など、他の公共事業による移転や補償の対象となっている場合は、補助金を利用できません。
解体後の固定資産税はどう変わるか
これは非常に重要なポイントです。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
しかし、建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。
補助金で解体費用を抑えられても、その後の税負担が重くなっては意味がありません。解体後の土地をどう活用するのか(売却、駐車場、新築など)を事前に計画しておくことが非常に重要です。
特定空家等に指定された場合の措置
空き家を放置し続け、倒壊の危険性が高いなど、周辺環境に悪影響を及ぼす状態になると、「特定空家等」に指定されることがあります。
特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態など、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家のことです。
特定空家等に指定されると、行政から助言・指導、勧告、命令といった措置が取られます。勧告を受けると、たとえ家が建っていても固定資産税の優遇措置が解除されてしまいます。 さらに、命令に従わない場合は行政代執行により強制的に解体され、その費用が所有者に請求されることもあります。
空き家を放置するリスクは非常に高いため、早めに解体や活用を検討することが賢明です。
補助金申請の4ステップと必要書類
補助金の申請は手続きが複雑に感じるかもしれませんが、基本的な流れは同じです。ここでは、一般的な4つのステップに分けて解説します。
ステップ1 事前相談と業者選定
まずは、補助金の担当窓口(奈良県や香芝市の担当課)に事前相談をしましょう。自分の所有する空き家が補助金の対象になるか、どのような手続きが必要かを確認します。
同時に、解体工事を依頼する業者を選定します。このとき、補助金申請のサポート実績が豊富な業者を選ぶと、手続きがスムーズに進むのでおすすめです。複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。
ステップ2 交付申請書の準備と提出
補助金を利用するには、必ず工事の契約・着工前に「交付申請書」を提出する必要があります。 業者から取得した見積書や工事計画書など、必要な書類を揃えて窓口に提出します。
主な必要書類の例
- 交付申請書
- 事業計画書
- 工事費用の見積書の写し
- 建物の位置図、現況写真
- 建物の登記事項証明書
- 所有者の住民票、市税の納税証明書
※制度によって必要書類は異なりますので、必ず担当窓口にご確認ください。
ステップ3 交付決定後の工事契約と着工
申請書を提出し、審査に通ると「交付決定通知書」が届きます。この通知書を受け取ってから、正式に解体業者と工事契約を結び、工事を開始します。
交付決定前に契約や着工をしてしまうと、補助金が受けられなくなるので絶対にやめましょう。
ステップ4 完了報告と補助金の受領
工事が完了したら、期限内に「完了実績報告書」を提出します。工事中の写真や、業者への支払い証明(領収書の写しなど)を添付する必要があります。
報告書の内容が審査され、問題がなければ補助金額が確定し、指定した口座に補助金が振り込まれます。補助金は後払いであることを覚えておきましょう。
補助金利用の注意点とよくある質問
最後に、補助金を利用する上での注意点と、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
注意点1 必ず工事着工前に申請する
最も重要な注意点は、必ず工事を始める前に補助金の申請を済ませることです。 すでに始まっている工事や、完了した工事は補助金の対象外となります。解体を決めたら、まず補助金の相談から始めるようにしましょう。
注意点2 申請期間と予算上限を確認する
補助金には、申請できる期間が定められており、多くの場合、年度ごとに予算の上限が設定されています。 人気の補助金は、受付開始後すぐに予算上限に達して締め切られてしまうことも少なくありません。公募が始まったら、できるだけ早く申請できるよう準備を進めておくことが大切です。
Q. 複数の補助金は併用できますか?
A. 工事内容が異なれば、併用できる場合があります。
例えば、「奈良県の補助金で耐震改修を行い、国の補助金で断熱窓の設置を行う」といったケースです。ただし、同じ工事に対して複数の補助金を受け取ることは原則できません。制度によって併用の可否が定められているため、利用したい補助金の担当窓口にそれぞれ確認が必要です。
Q. 申請すれば必ずもらえますか?
A. いいえ、必ずもらえるとは限りません。
補助金は、申請内容の審査を経て交付が決定されます。書類に不備があったり、条件を満たしていなかったりすると不採択になることがあります。また、前述の通り、申請者が多く予算の上限に達した場合は、先着順や抽選となり、受け取れないこともあります。
補助金に詳しい解体業者の選び方3つのコツ
補助金の手続きをスムーズに進め、安心して工事を任せるためには、信頼できる解体業者選びが不可欠です。ここでは、業者選びで失敗しないための3つのコツをご紹介します。
補助金申請のサポート実績で選ぶ
補助金の申請は、必要書類が多く手続きも煩雑です。補助金の利用実績が豊富な業者であれば、書類作成のサポートや、手続きの段取りについて的確なアドバイスが期待できます。 業者のホームページで実績を確認したり、問い合わせの際に直接質問してみましょう。
建設業許可・解体工事業登録を確認する
解体工事を行うには、「建設業許可(建築一式工事、土木一式工事、解体工事のいずれか)」または「解体工事業登録」が必要です。無許可・無登録の業者は違法であり、不法投棄や高額請求などのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。 必ず許可・登録の有無を確認しましょう。
複数社から相見積もりを取得し比較する
解体費用は業者によって大きく異なります。必ず3社程度の業者から相見積もりを取り、費用と工事内容を比較検討しましょう。 金額の安さだけで選ぶのではなく、見積書の内訳が明確か、担当者の対応は丁寧か、質問にしっかり答えてくれるかといった点も重要な判断基準になります。
まとめ
今回は、香芝市の解体補助金に関する最新情報と、代わりに利用できる奈良県や国の制度、申請のポイントについて解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 2024年現在、香芝市単独の解体補助金は受付を終了している。
- 代わりに「奈良県住まいの安全・安心・快適・省エネ・長寿命化促進事業」などの県の制度が利用できる可能性がある。
- 解体後のリフォームには「香芝市三世代同居・近居促進事業」や国の「子育てエコホーム支援事業」も検討できる。
- 解体すると固定資産税が上がる可能性があるため、事前の計画が重要。
- 補助金は必ず「工事着工前」に申請し、予算や期間に注意する。
- 補助金申請の実績が豊富で、信頼できる解体業者を選ぶことが成功の鍵。
空き家の解体や補助金の手続きは、専門的な知識が必要で難しく感じるかもしれません。そんな時は、まず補助金申請のサポート実績が豊富な解体業者に相談してみるのが一番の近道です。
あなたの状況に合った最適なプランや、利用できる補助金について、プロの視点からアドバイスをもらえます。この記事が、あなたの解体計画をスムーズに進める一助となれば幸いです。
10分で完結!即日見積
どこよりも「安く」「速く」対応いたします!


